子どもに「なんで5月5日なの?」と聞かれて、答えられますか?

「どうして子供の日って5月5日なの?」「鯉のぼりってなんで飾るの?」
ある日、子どもにそう聞かれて、ふと考え込んでしまった… そんな経験ありませんか?
実は、私たち大人でもきちんと答えられる人って意外と少ないんです。
今回は、子供の日の由来や、5月5日という日付の意味、鯉のぼり・柏餅・兜(かぶと)などの飾りに込められた思いや理由を、分かりやすく紹介します!
子供の日=「男の子の日」じゃない? 本当の意味とは…
子供の日の由来は、もともと「端午の節句(たんごのせっく)」という中国から伝わった風習です。
端午とは?「旧暦5月初めの“午(うま)の日”を指す言葉」
端午とは、もともとは「月の端(はじめ)の午の日」という意味から来ています。
「端」は始まり、「午」は5月を意味し、端午は5月の最初の午の日に行われることからこの名前がついています。
そして、日本では奈良時代からこの行事はあったとされており、厄除けや健康を願う日として大切にされてきました。
その後、武士の時代になると、「鎧兜=戦う男の象徴」になったことで、男の子の健やかな成長を願う日へと変化します。
戦後、すべての子どもと家族を祝う日に変化
しかし、現在の「子供の日」はそれだけではありません。
戦後の1948年(昭和23年)に正式な国民の祝日として制定されたときには、次のように定められました。
子どもの人格を重んじ、子どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
なぜ、母親だけ?
ちょっと時代錯誤な気もしますが…。戦後に「子どもの日」を定めた際、母親が主に子育てを担っていた時代背景があったためと言われます。そのため、母への感謝が祝日の趣旨に含まれました。
つまり、すべての子どもと母親(家族)を祝う日なんです。
男の子だけでなく、女の子にも意味のある日なんですね。
鯉のぼりや柏餅、兜にはそれぞれ理由がある
なんとなく毎年飾っている鯉のぼりや兜、食べている柏餅。
実は、それぞれにちゃんとした意味や願いが込められています。
◆ 鯉のぼり|「逆境を乗り越える力」

鯉のぼりが空を泳ぐ姿には、ある中国の伝説が関係しています。
「黄河の滝を登りきった鯉は、龍になる」
──そう信じられていました。
つまり、「困難を乗り越え、立派な大人になるように」という強い願いが込められているのです。
空高く泳ぐ鯉のぼりには、親の希望がぎゅっと詰まっているんですね。
◆ 兜(かぶと)|命を守る

なぜ鎧兜を飾るのか?
それは、「身を守るもの」=「大切な子の命を守る願い」が込められているからです。
武将の兜には「家族を守る覚悟」が宿っていました。
それを子どもに託すことで、「強く優しく育ってほしい」という親の想いが表現されているのです。
◆ 柏餅(かしわもち)|「家系のつながり」を願う縁起物

柏の葉は、新芽が出るまで古い葉が落ちないという特徴があります。
このことから、
「家系が絶えない」「子孫繁栄」
という縁起物として食べられるようになりました。
今では「子供の日には柏餅」として、自然と受け継がれていますが、実はとても深い意味があったのです。
なぜ5月5日なの?「5」の数字に隠された理由

「なぜ5月5日なのか…?」
これは偶然ではありません。
中国の陰陽思想〔すべての物事は、相反する力(陰と陽)のバランスで成り立っているという考え方〕では、奇数は縁起が良い「陽の数」とされています。
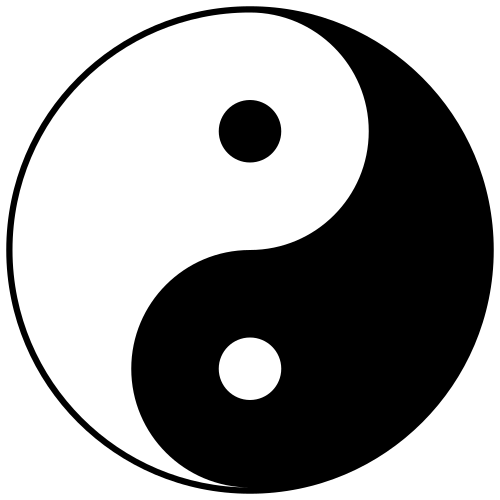
特に「5」はバランスの取れた数で、「成長・繁栄・中心」の象徴。
そんな「陽」の数字が重なる5月5日は、最も強い生命力が宿る日と考えられてきたのです。
まとめ|5月5日はすべての子どもたちの健やかな未来を願う日

- 子供の日は「命を守る」文化から生まれた祝日
- 鯉のぼりは「逆境に打ち勝つ」象徴
- 兜は「災いから身を守るお守り」
- 柏餅は「家系が続く」縁起物
そして、「子どもの日」は、子どもの幸せを願うだけでなく、家族の未来を考える一日でもあります。
この機会に、子どもと一緒に話すきっかけにしてみてはいかがでしょうか!




