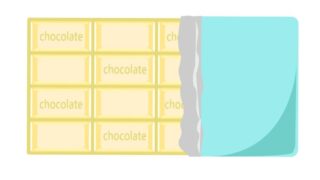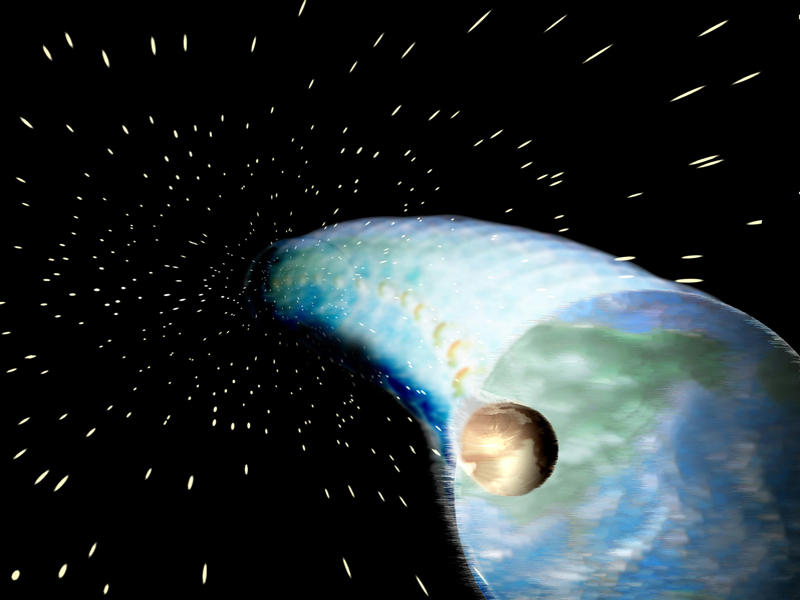日本の花火大会の起は「隅田川花火大会(両国川開きの花火)」

日本の打ち上げ花火のはじまりは、江戸時代に遡るそうです。
1733年(享保18年)に江戸幕府の八代将軍の徳川吉宗が打ち上げた、

〔暴れん坊将軍 徳川吉宗〕
現在の「隅田川花火大会」、当時の「両国川開きの花火」がはじまりと言われています。
日本で最初にビールを飲んだ人は、あの暴れん坊将軍だったかもしれない…?

そのころ、日本は記録的な飢饉(ききん)〔 気候や害虫などで農作物のできが悪く食糧が欠乏すること〕『享保の大飢饉(きょうほうのだいききん)』にみまわれ、約1万人以上の死者〔実際はその10倍以上とも…〕が出ていたそうです。
更に、江戸時代にはコレラ〔コレラ菌が混入した飲食物を介して感染する急性下痢症。当時は多くの死者を出した〕によって多くの死者が出ていたこともあり、死者の供養と悪疫退散の意味で、水神祭のときの余興として20発の花火を打ち上げたのが花火大会の起源と言われています。
『花火』の歴史

花火のはじまりは「中国の秦の始皇帝の時代」
所説ありますが、『花火』は、中国の秦の始皇帝の時代で紀元前3世紀ごろに発明されたとされています。
花火といっても、元々は『狼煙(のろし)』〔合図のために火薬などで高くあげる煙〕として利用していた火薬からはじまったと言われ、主に戦の用途として作られたとされています。
日本に火薬が伝わったのは「鉄砲伝来」
日本に火薬が伝わったのはかなり後のことで、1543年(天文12年)、鉄砲が初めて伝来した際のことでした。
ポルトガル人が種子島に漂着した際に、火縄銃とともに火薬も日本にもたらされたのです。この火薬は、当初はもちろん戦いのために使用されました。

日本ではじめて鑑賞用の花火を見たのは「徳川家康」
そしてその後、観賞用としての『花火』に関わった人物は、江戸幕府を開いた徳川家康だったといわれています。

1613年(慶長18年)、イギリス国王の使節(しせつ)〔国の命令を受け他国に派遣される人〕を駿府城(すんぷじょう)〔家康が晩年を過ごした城〕に迎えたとき、鉄砲などを献上されたようなのですが、その時、花火を鑑賞したということが江戸時代の文書に記録が残っているそうです。
当時は『手筒花火』といった竹の筒を利用した手持ち花火だったのですが、


新しい物好きの家康は、幕府を開いたのち弾薬としての火薬の製造を禁止していたものの、三河の鉄砲隊に花火の製造を命じたようで、やがて江戸にも花火が広まったとされています。

その後、花火師と呼ばれる専門の職人が現れ、花火の技術と芸術が発展していくということなのです。