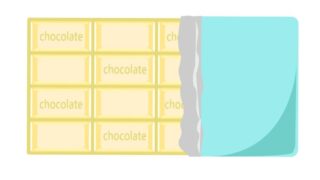川にもランクがあるって知ってましたか?

一級・二級・三級(または準用)河川。―― この等級は、川の “重要度” や “誰が管理しているか” を示しています。
けれども、「一級だから大きい川?」「三級ってあるの?」と疑問に思う人も多いはずです…。
今回は、堅苦しい法律用語をやさしく噛み砕いて、 “川のランク制度” を楽しく理解できるようにまとめてみました!
川の “ランク” とは?:イメージをつかもう!

川にも学校の成績表みたいなランク付けがされています。
違いをざっくり言うと──
- 🏞 1級河川 ⇒ 国が管理! 全国的に大事な “メイン河川”
- 🚣 2級河川 ⇒ 都道府県が管理! 地域の “頼れる川”
- 🏡 準用(3級)河川 ⇒ 市町村が管理! 地元密着の “小さな川”
例えば、日本を代表する「利根川」や「淀川」は「一級」。
その支流〔大きな川に合流する小さな川〕や、地域の農業を支える中規模の川が「二級」。
そして、公園横を流れるような小川が「三級(準用)」というイメージになります。
「二級河川】という標識(看板)は存在するの?

二級河川の標識(看板)は、基本的に存在します。
ただし、一級河川のように全国共通のデザインで整備されているわけではなく、設置は都道府県の判断でデザインもまちまちです。
例えば、神奈川県・福岡県・北海道などでは「二級河川 ○○川」と書かれた標識が実際にあります。
一方で、東京都や大阪府などでは標識がないことも多いようです。
それぞれの “管理者” と “役割” を見てみよう!

🏞 一級河川 — 国が本気で守る「日本の大動脈」
一級河川は、国土交通大臣が指定する、全国的に重要な川。
流域が広く、洪水対策や利水計画が国レベルで必要な川が対象です。
➡ 例:利根川・信濃川・木曽川 などなど

大規模な治水工事〔洪水を防ぐための川の整備〕やダム建設など、国の直轄事業も多く行われます。
一級河川は全て国が直接管理してるの?

Q :一級河川って全部、国が直接管理してるの?
→ 実は違います!
一級河川といっても、すべての区間を国(国土交通省)が直接管理しているわけではありません。
国が管理しているのは、「直轄区間(ちょっかつくかん)」と呼ばれる、特に重要な部分だけです。この直轄区間では、堤防の整備や水害対策などを国が直接行います。
一方で、それ以外の区間、たとえば支流や上流の地域などは、都道府県が管理者となって整備や維持を行っています。
🚣 二級河川 — 都道府県が守る「地域の命綱」

二級河川は、都道府県知事が指定して管理します。
その地域の経済や農業、生活を支える川が中心。
➡ 例:神奈川県の「酒匂川」、熊本県の「白川」などなど
地域住民にとっては “防災の要”。県の防災計画にも深く関わります。
🏡 準用(3級)河川 — 市町村が見守る「まちの小川」

一級・二級に当てはまらない小規模な川は、市町村が管理します。
正式には「準用河川」と呼ばれ、河川法の一部だけが適用されます。
➡ 例:通学路沿いや田んぼの脇を流れる小川など
身近だけど、地域の排水や安全にとって欠かせない存在なんです。
よくあるギモン!「普通河川」と「3級河川」の違い

実は、「普通河川」と「3級河川」はまったく別ものなんです。
そして、現在の河川の分類は、「一級河川」「二級河川」「準用河川」「普通河川」の4つで、「3級河川」という区分はすでに存在しません。
では、どんな違いがあるのかをわかりやすく整理してみましょう👇
河川の区分(等級)と特徴を比べて見よう!
| 区分 | 河川法の扱い | 管理者 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 一級河川 | 河川法の「適用」 | 国・都道府県 | 国が指定。流域が広く、国土保全に重要な川(例:利根川・淀川など) |
| 二級河川 | 河川法の「適用」 | 都道府県 | 地域の生活・産業に関係の深い川(例:多摩川の一部など) |
| 準用河川 | 河川法の「準用」 | 市町村 | 比較的小規模だが、公共的な管理が必要な川(市町村が指定) |
| 普通河川(法定外河川) | 河川法の「適用・準用なし」 | 市町村 | ごく小さな川や用水路など。条例などに基づいて市町村が管理 |
💡 「3級河川」は昔の呼び方!
かつて(昭和初期頃)、「3級河川」という区分が使われていた時代がありました。
しかし、昭和39年(1964年)の河川法改正によって制度が見直され、現在では「一級」「二級」「準用」「普通」という形に統一されています。
つまり、「普通河川」は河川法の対象外の小規模な川で、市町村が地域密着で管理する身近な水路なんです。
どうやって “等級” が決まるの?

「川のランク」は大きさだけで決まるわけではありません。
決め手になるのは、どれだけ人々の生活や国の安全に関わるか。
| 判断ポイント | 内容の例 |
|---|---|
| 流域面積 | 広い流域ほど上位等級になりやすい |
| 影響範囲 | 多くの人・町に影響する川は重要度が高い |
| 治水・利水の必要性 | 洪水・水利用の重要度で判断 |
| 管理体制 | 国 or 県 or 市町村のどこが適しているか |
つまり、 “その川がどれだけ社会に影響を与えるか” がカギなんです!
🏠 実は等級を知ることはとても大事!暮らしの中で役立つ豆知識

私たちの暮らしに密接に関わる「豆知識」として役立つポイントを見てみましょう!
🏠 不動産を買うとき
川の等級(一級・二級・普通)によって、その地域での工事や土地利用に関するルールが変わることがあります。
たとえば、
- 一級・二級河川では「河川法」に基づき、堤防近くでの建築や造成に制限がある。
- 普通河川では、市町村の条例や管理規定に従う必要がある。
つまり、川の等級を知っておくことで、将来的な建築計画や資産価値にも関わる判断材料になるのです。
🌧 洪水や防災マップの確認
もし洪水が起きたとき、その川を「誰が管理しているか(国・県・市町村)」を知っておくと、災害時にどの機関が発表する情報をチェックすべきかが分かります。
- 一級河川 → 国土交通省や都道府県が発信する情報
- 二級河川 → 都道府県の防災情報
- 普通河川 → 市町村のハザードマップや避難情報
👉 防災マップを確認するときは、川の等級を合わせてチェックしておくと安心です。
🌿 環境活動・清掃ボランティア
地域の川をきれいにしたいと思ったら、管理者によって問い合わせ先や許可の取り方が違う点にも注意が必要です。
- 一級河川 → 国または都道府県の河川事務所
- 二級河川 → 都道府県土木事務所
- 普通河川 → 市町村役場の建設課や環境課
つまり、どの等級の川かを知るだけで、「誰に相談すればいいか」がすぐ分かるんです。
💡 実は、川の等級は川の分類だではなく、安全・防災・まちづくりに関わる生活の知恵なんです。
まとめ:「川のランク」は人と自然をつなぐ “ルールブック”

一級・二級・三級(準用)河川の違いをまとめると──
| 区分 | 管理者 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 🏞 一級河川 | 国土交通大臣 | 全国レベルで重要な治水・利水 |
| 🚣 二級河川 | 都道府県知事 | 県単位の地域防災・水管理 |
| 🏡 準用河川 | 市町村長 | 生活に密着した小規模河川 |
「川のランク」とは、水の流れを守る “責任の分担表” のようなもの。規模や重要度に合わせて、国・県・市がそれぞれ役割を担っています。
普段は何気なく見ている川にも、こんなにしっかりとした仕組みがあるなんて、ちょっと面白いですよね!