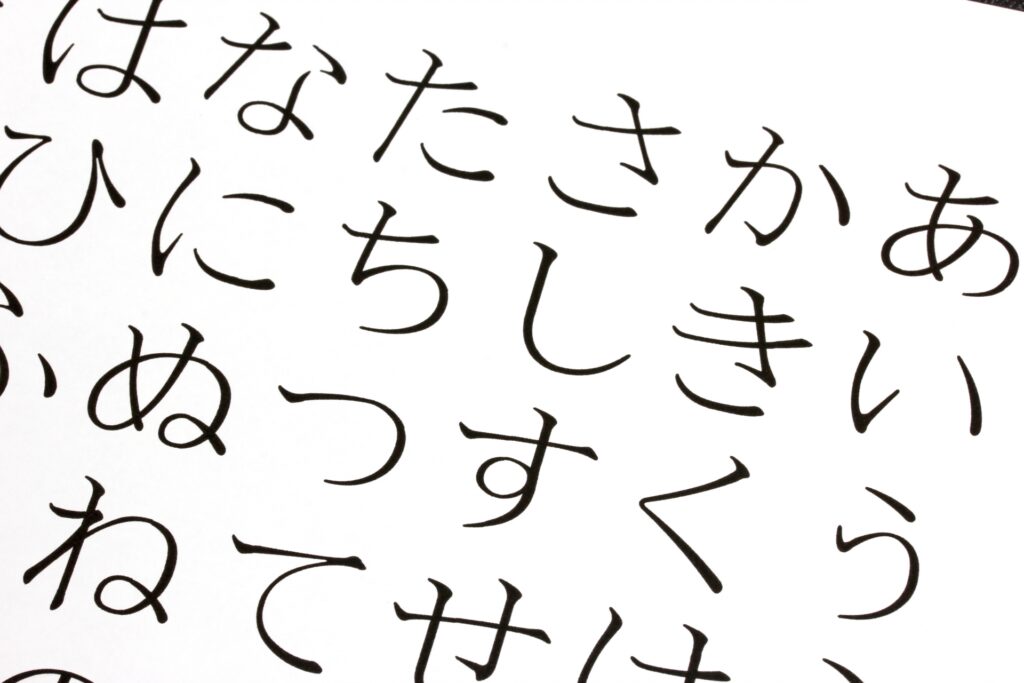信号機はいつから?

現在ではどこでも見かける信号機にも始まりがあったわけですが、いつから使用されるようになったのでしょうか…?
それでは、見ていきましょう!
世界初の信号機
世界初の信号機は、1868年でイギリスのロンドン市内ウエストミンスターに設置されました。

当時、多かった馬車の事故を回避する為に設置されたそうですが、現在のような電気信号機ではなく、ガスを使用した信号機だったため、ガス爆発を起こして、わずか3週間で撤去になったそうです。
ちなみに、その頃の日本はというと、ちょうど明治元年で、戊辰戦争(ぼしんせんそう)〔旧幕府軍と新政府軍の戦い〕の時代ということになります…
日本で最初にビールを飲んだ人は誰…?あの暴れん坊将軍だったかもしれない…?
世界初の「電気」信号機

世界で最初の【電気式交通信号機】は、1914年にアメリカ・オハイオ州クリーブランドに設置されました。これが「電気式」という点では最初とされます。

そして、1918年(大正7年)、ニューヨークの5番街と42丁目の交差点に設置された信号機は、より洗練された自動式・3色式の信号機。つまり、初の「3色式電気信号機」が登場したのです。
日本初の信号機

そして、1930年(昭和5年)に日本にもアメリカから信号機が輸入され、東京の日比谷交差点で初めて設置されることになりました。
設置された頃、ほとんどの歩行者はそれまで見たことがない信号機にピンとこなく、ただあるだけの状態で、信号を守っていたのは路面電車だけだったそうです。
どうして緑なのに青信号?

青りんごや青野菜、青信号など、緑色なのに、なぜか『青』という言葉をつかいますが、どうしてなのでしょうか…?
昔は『白』『黒』『赤』『青』の4色しかなかった
今では、色を表す言葉が沢山ありますが、平安時代末期頃までの日本には色を表す言葉が『白』『黒』『赤』『青』の4つしかなく、その4色によって、あらゆる色を表現していたと言われています。
日本で約1,200年も続いた肉食タブーの文化とは…?当時は肉を薬として食べていた…
当時は色といっても、主に、光に対する明るさを表していたとされており、
明るい色 → 『白』
暗い色 → 『黒』
そして、
赤、黄色など → 『赤』
青、緑、紫、灰色など → 『青』
のように表現していたそうです。
特別扱いの『白い』『黒い』『赤い』『青い』とは
現代でもこの4色は、特別の扱いをされている節があり、そのまま形容詞〔 事物の性質や状態などを表す〕の【~い】を付けることができます。
『白い』『黒い』『赤い』『青い』
他にも、
『白々と(しらじらと)』 『黒々と(くろぐろと)』
『赤々と(あかあかと)』 『青々と(あおあおと)』
というような言葉も、この4色のみでしか使うことができず、古代の名残といえそうです。
昔は『緑色信号』という名で法律により定められていた
そして、本題の信号機に使われている色もほぼ緑色ですが、現在の日本では『青信号』と呼ばれています。
けれども遡ること1930年頃、日本で初めて信号機が設置された頃は『緑色信号』という名で法律によって定められていたそうです。
しかし、1947年に法律が改正され『青色』となりました。
その背景には、やはり日本人ならではの考え方あったのか、新聞などのマスメディアをはじめ、国民も『緑色』という言葉に馴染むことが出来ず、『青色』に変えることになったと言われています。