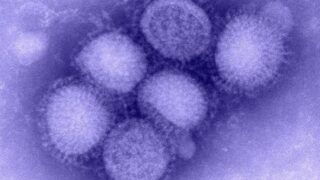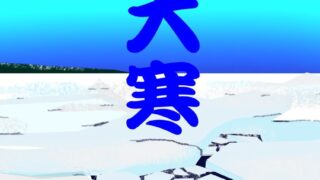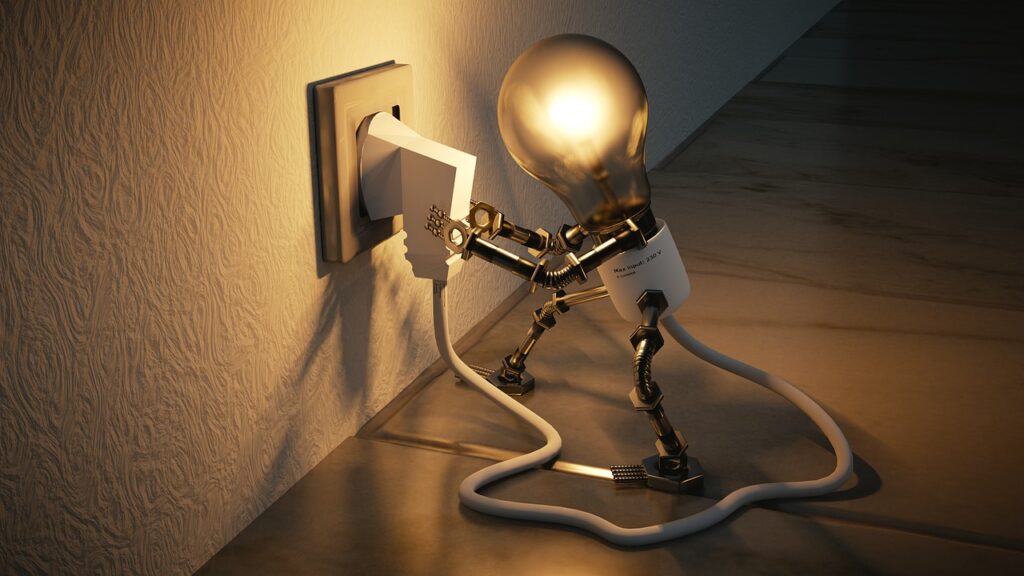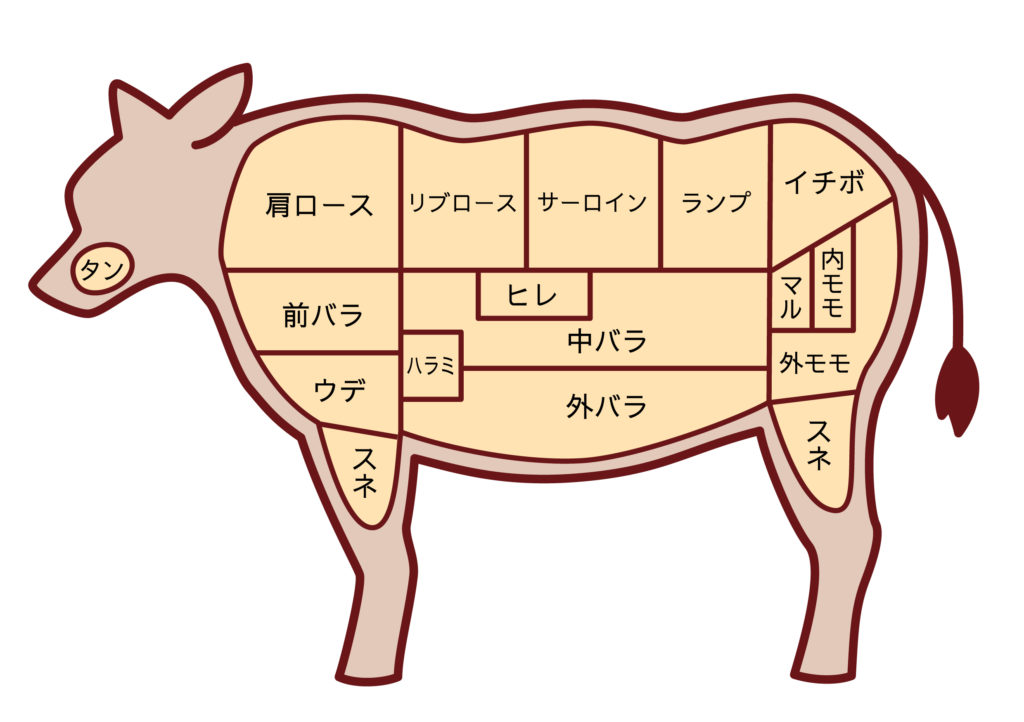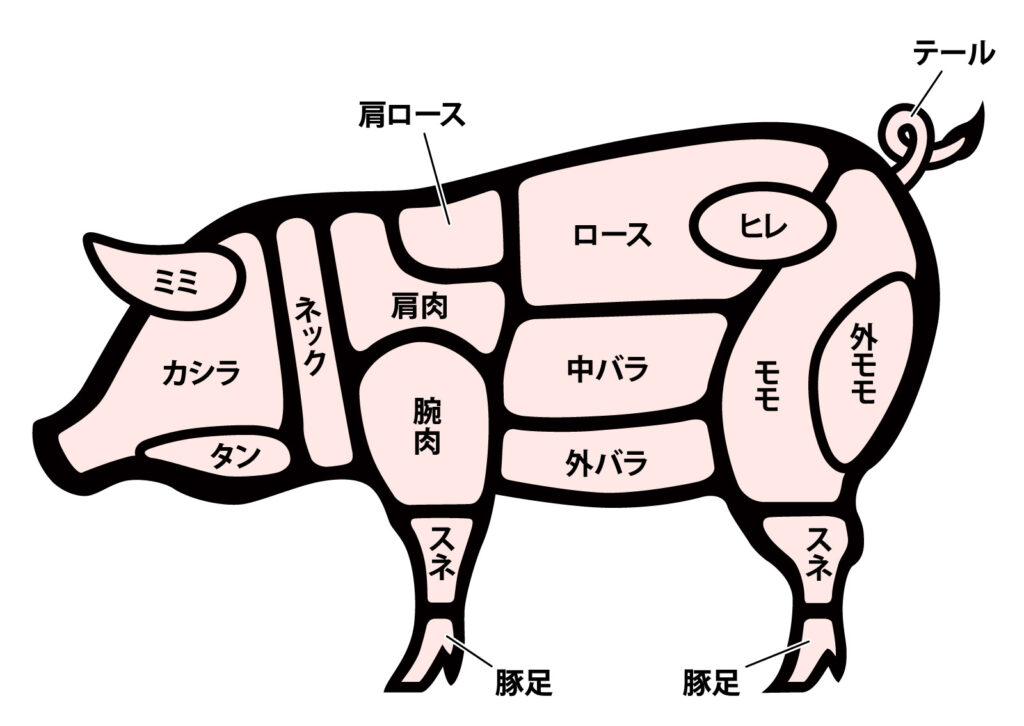牛の部位
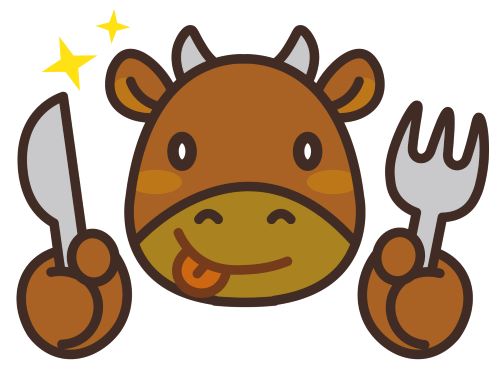
肉屋さんや焼肉屋さんなどにいくと、いろいろな牛肉の部位がありますが、いったいどこの肉なのでしょうか…?
[ 牛 正肉 ]
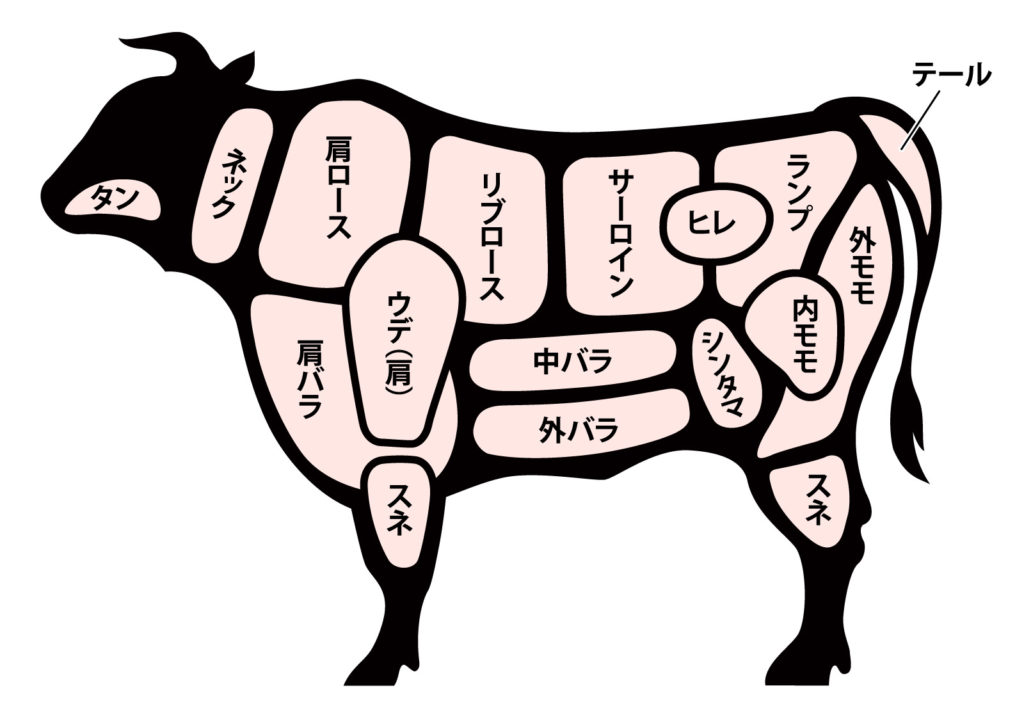
【 ネック 】
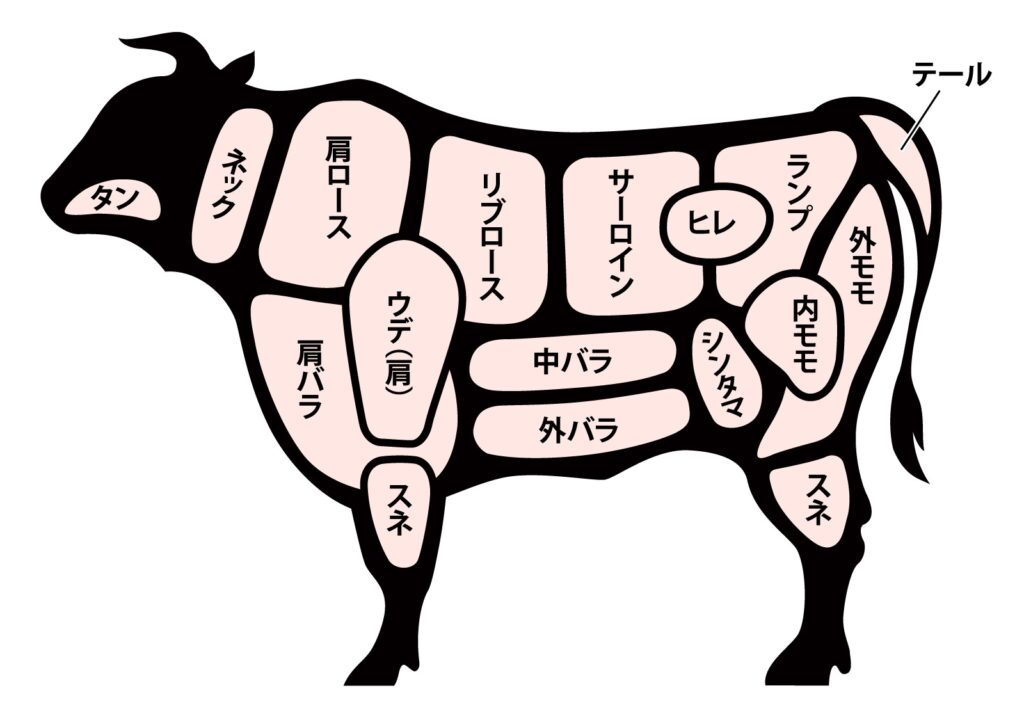
首筋の肉。赤身が多く肉はかため。
煮込み料理やコンビーフなどによく使われる。
【 かた 】
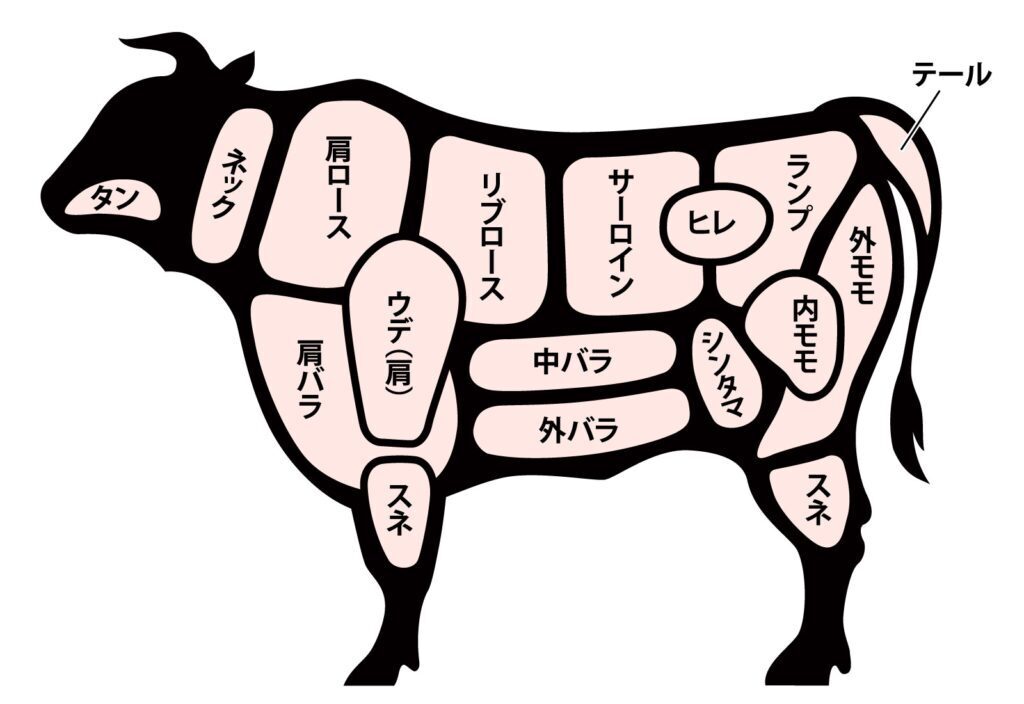
前足の付け根の近くで肩甲骨(けんこうこつ)の外側にある肉。
赤身で脂肪が少なくややかため。
煮込み料理などによく使われる。
【 かたロース 】
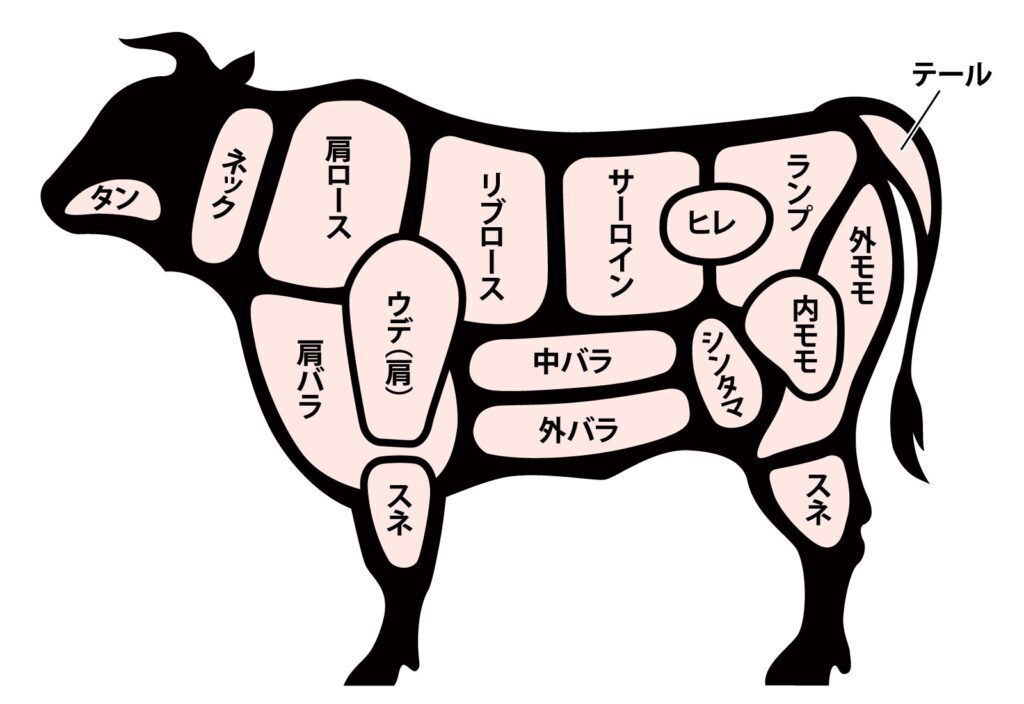
頭の付け根の近く〔首に近い側〕、背骨の両脇にある肉。ばら肉に近い筋肉も含む。
霜降り〔赤身に脂肪が網の目に入る〕にもなり、
しゃぶしゃぶやすき焼きなどでよく使われる。
※ロースとは、肩から腰にかけての柔らかい上等な肉をいう。
【 リブロース 】
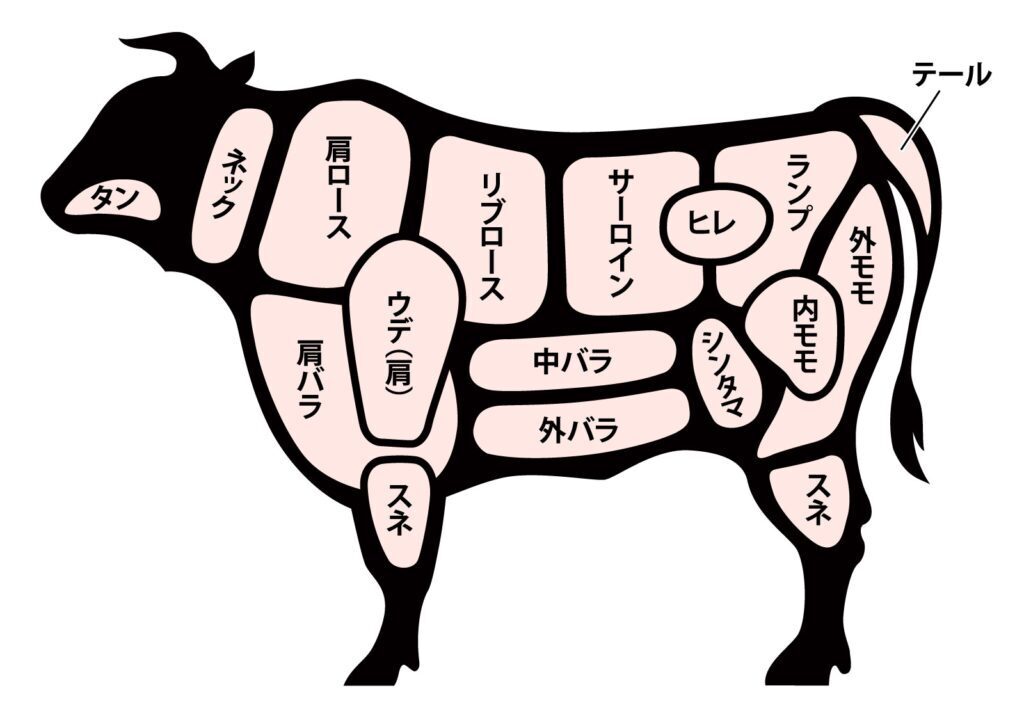
かたロースから続く背骨の肉。
霜降りに一番なりやすい。肋骨がついた状態のものをチョップという。
※リブは英語で肋骨の意味。
【 サーロイン 】
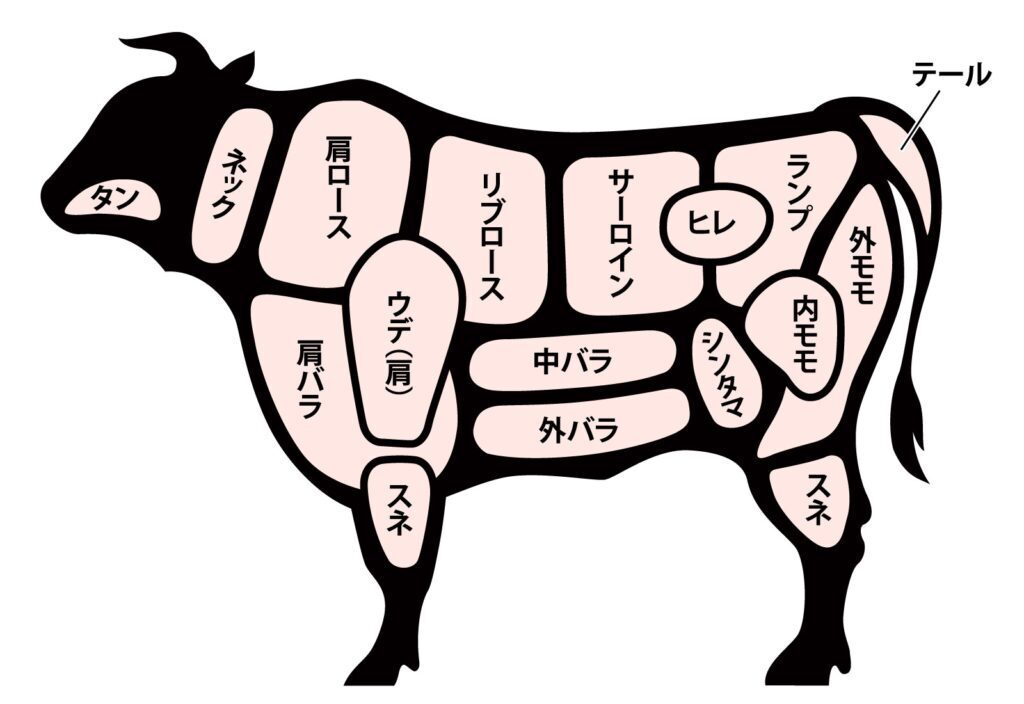
背中の中央部の細長い肉。ヒレの外側で、リブロースとらんぷの間のロース。
霜降りにもなり、ステーキでよく使われる。
【 ヒレ 】
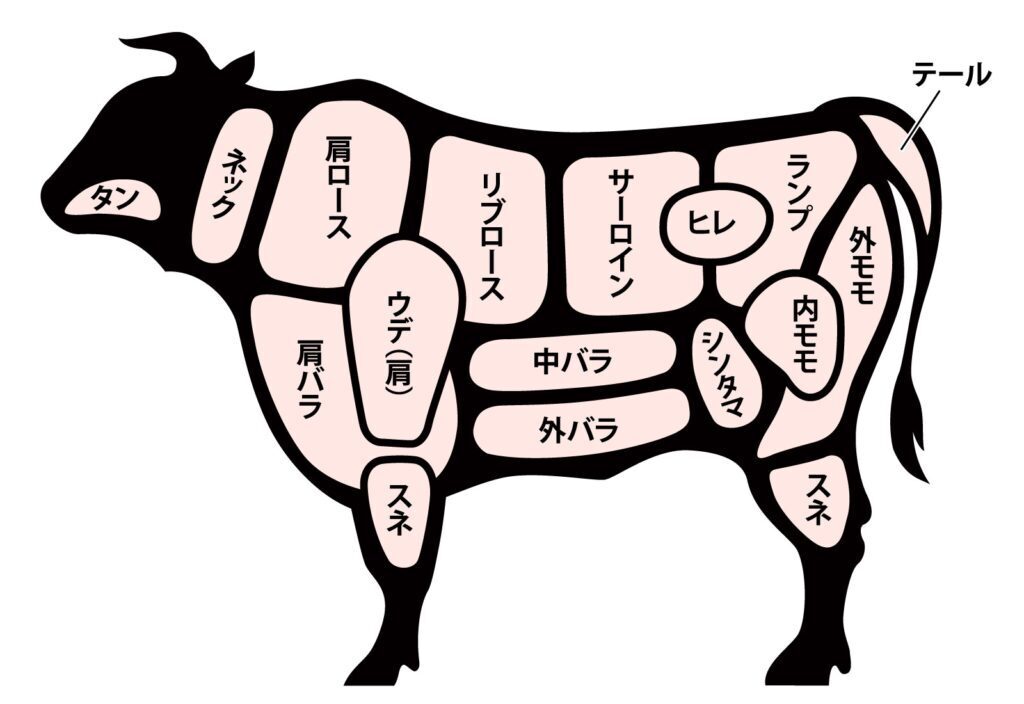
サーロインの内側で、脂肪が少なく柔らかい部分。
シャトーブリアンは、ヒレの中央部で牛肉の最高級部位。
※ヒレ(フィレ)はフランス語。英語ではテンダーロインという。
【 ばら 】
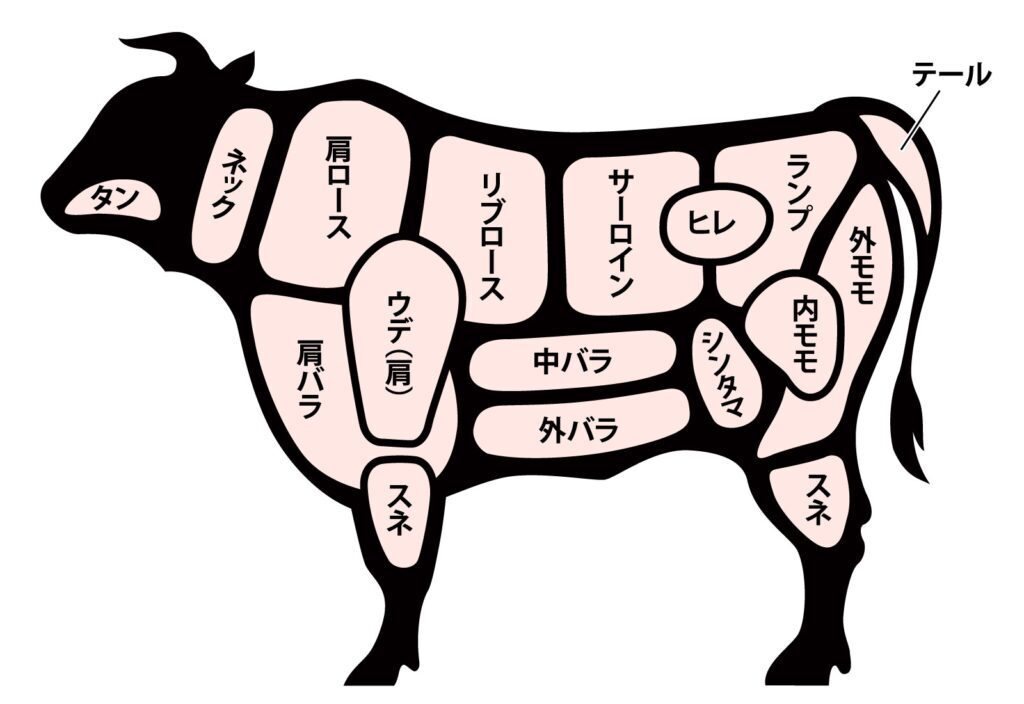
あばら骨の周りの肉。赤身と脂肪が層になっている。
焼肉によく使われる。
※カルビは韓国語の肋骨(あばら)の意味。
【 もも 】
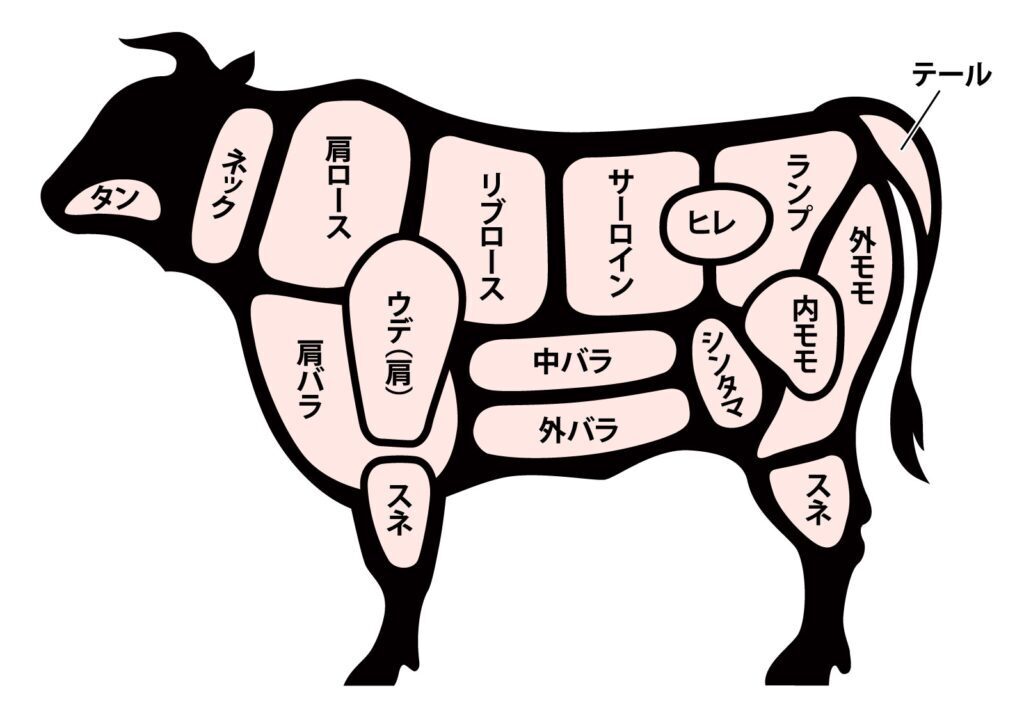
内ももの肉。赤身で大きな塊の肉。
ローストビーフやステーキによく使われる。
だるまは、内ももで柔らかい部分をいう。
シンタマは、内ももの下部。赤身。
【 そともも 】
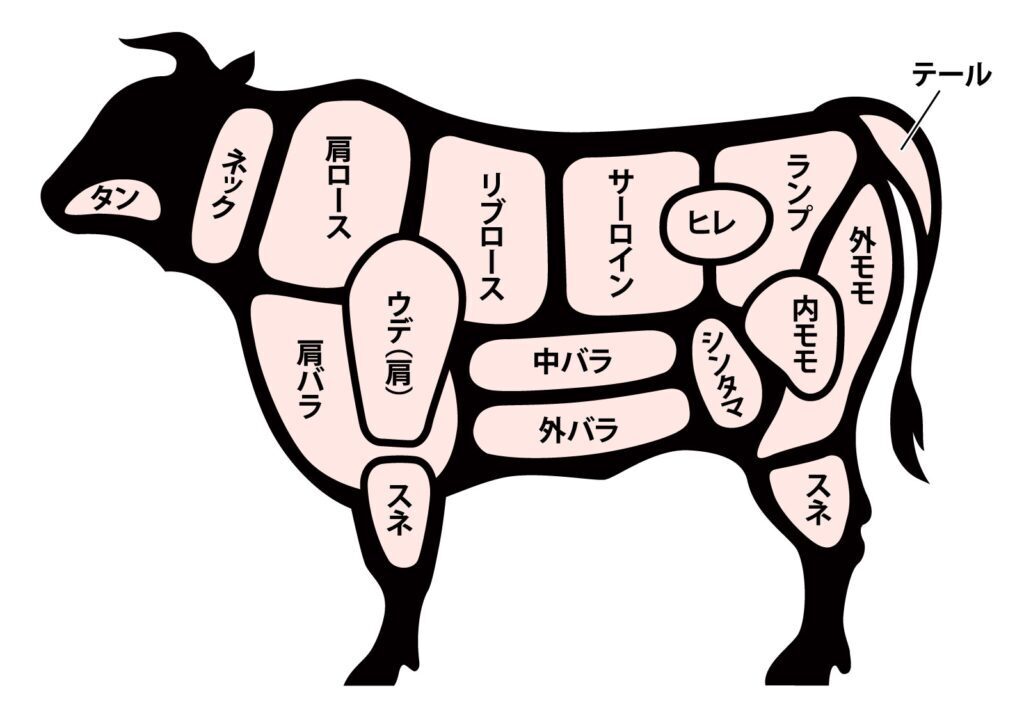
外ももの肉。内ももに比べると、きめがやや粗くややかたい。
炒め物や煮込みなどによく使われる。
【 らんぷ 】
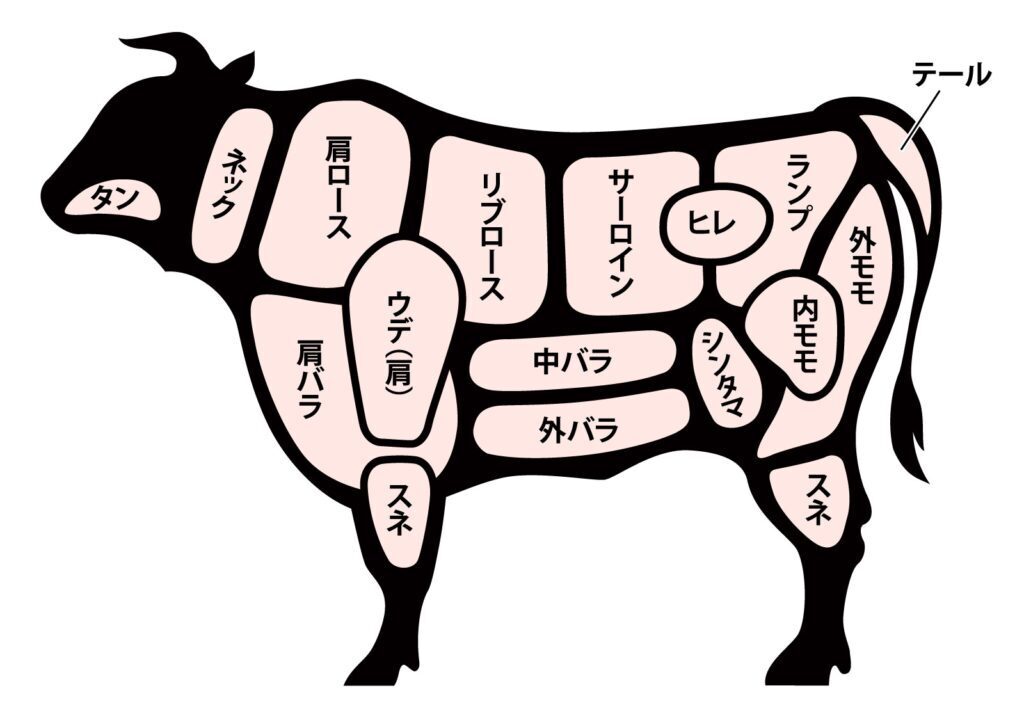
もも肉のお尻に近い柔らかい部分。赤身が多い。
ステーキによく使われる。
【 すね 】
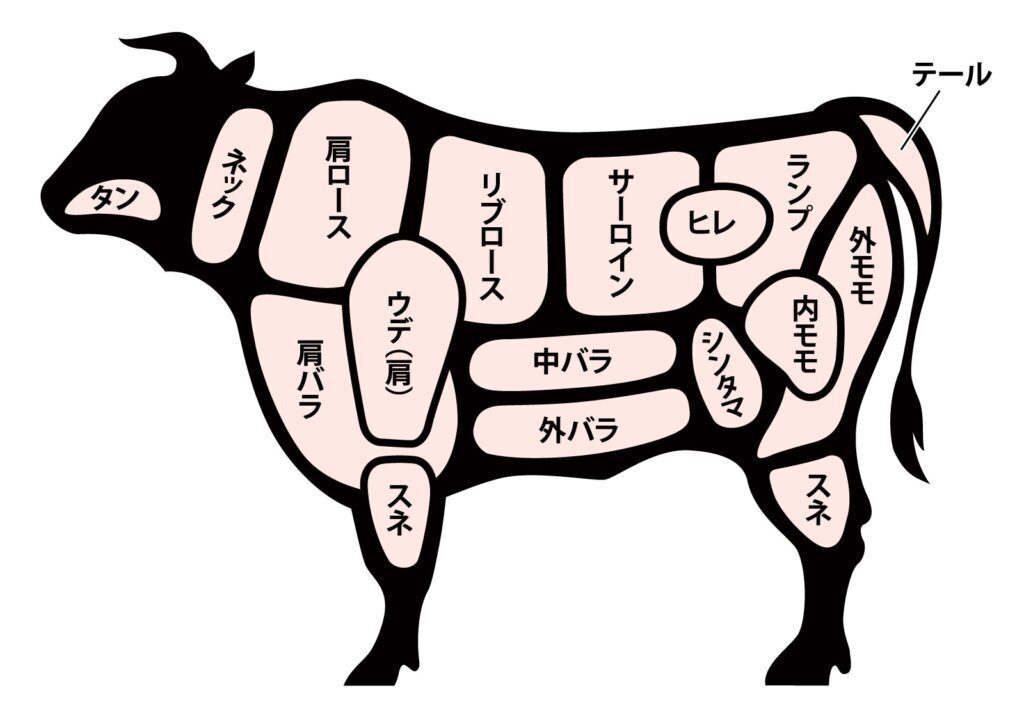
すねの肉。筋があって肉はかため。
長時間の煮込み料理などで柔らかくなる。だしにも使われる。
ソーセージ、ハム、ベーコン製法の違いとは?ウインナー、フランクフルト、ボロニア…
[ 牛 内臓 ]
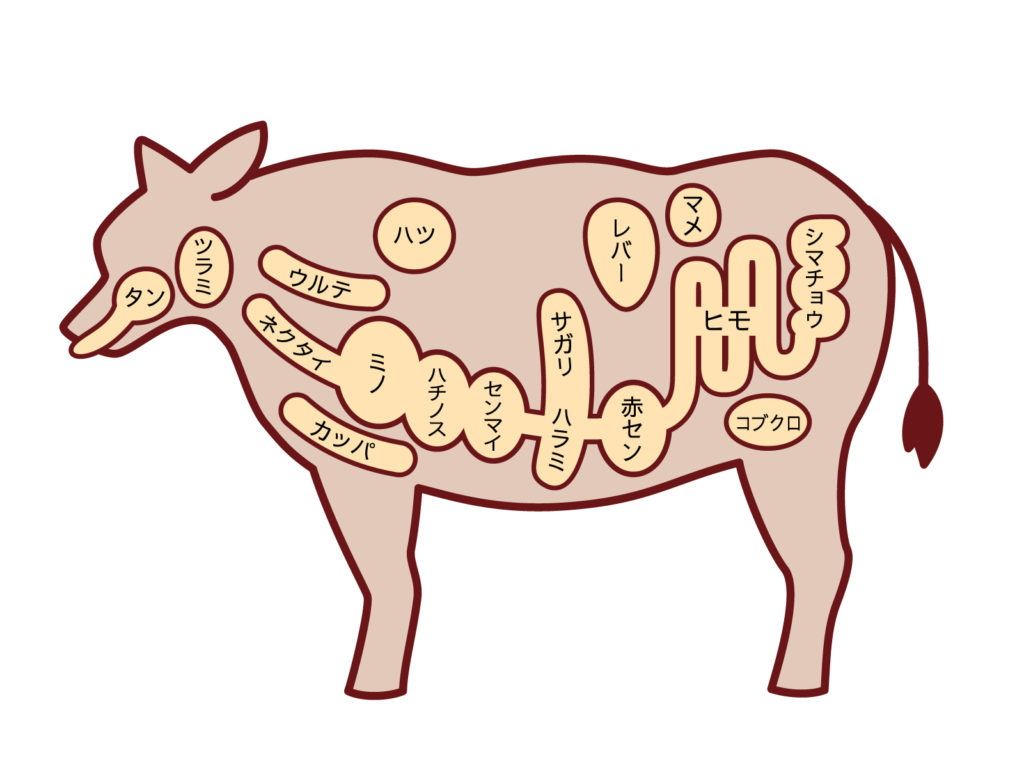
【 タン 】
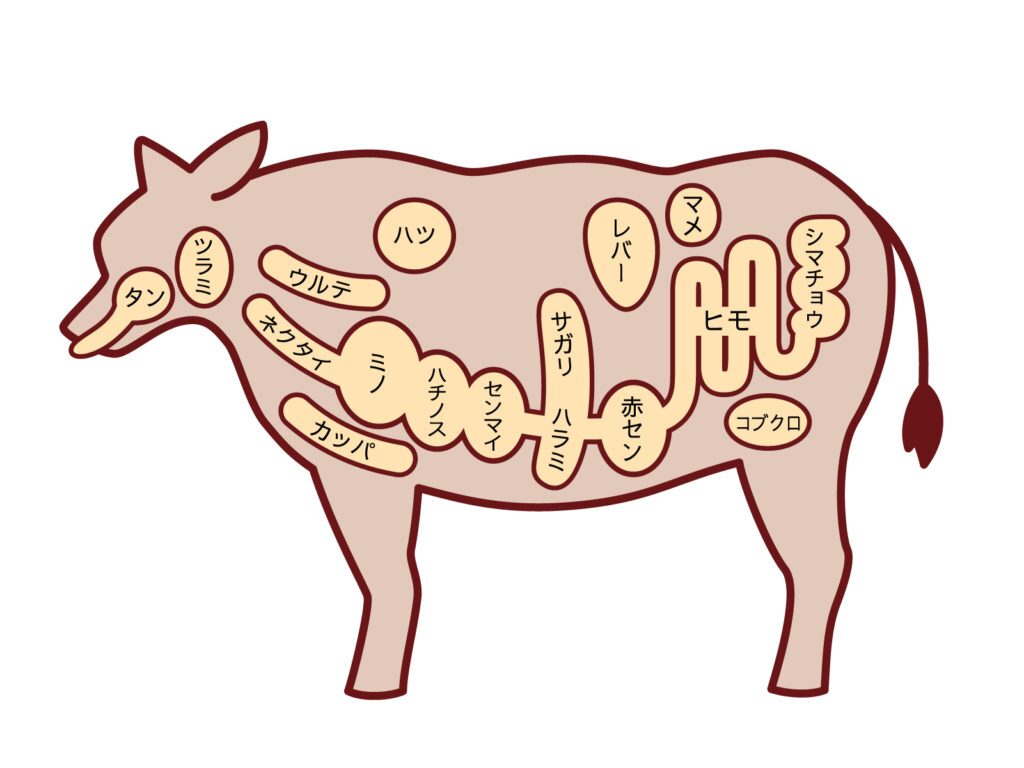
舌。根元の方が柔らかい。
【 ツラミ 】
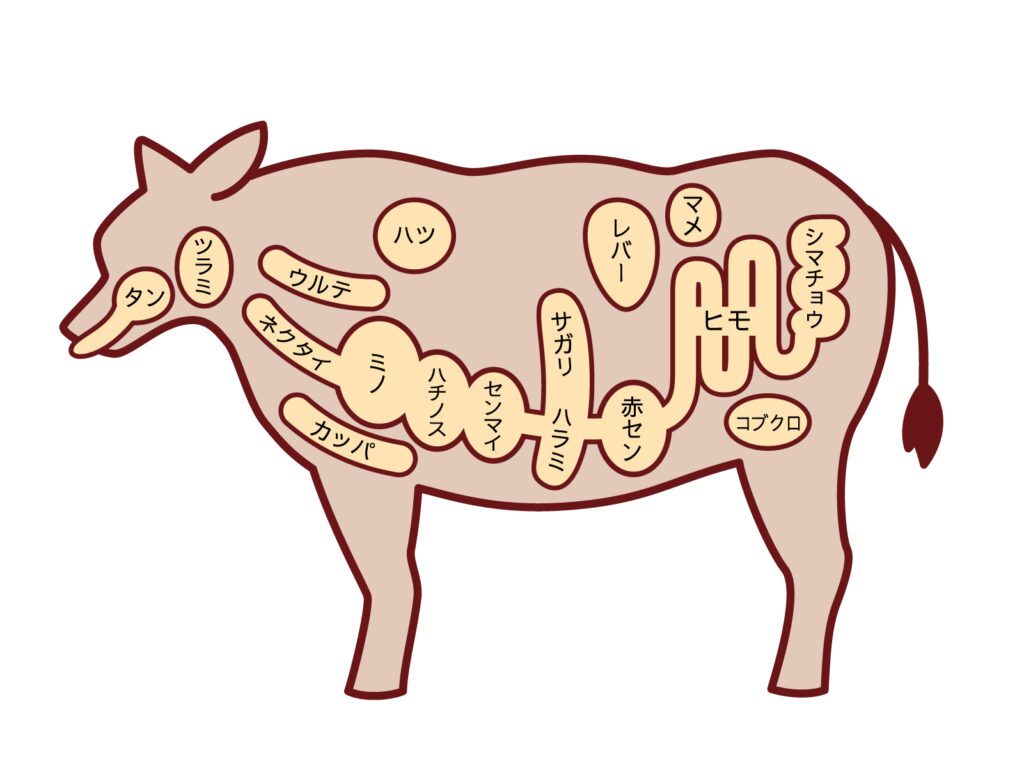
ほほ肉。赤身でゼラチン(コラーゲン)を多く含む。
【 レバー 】
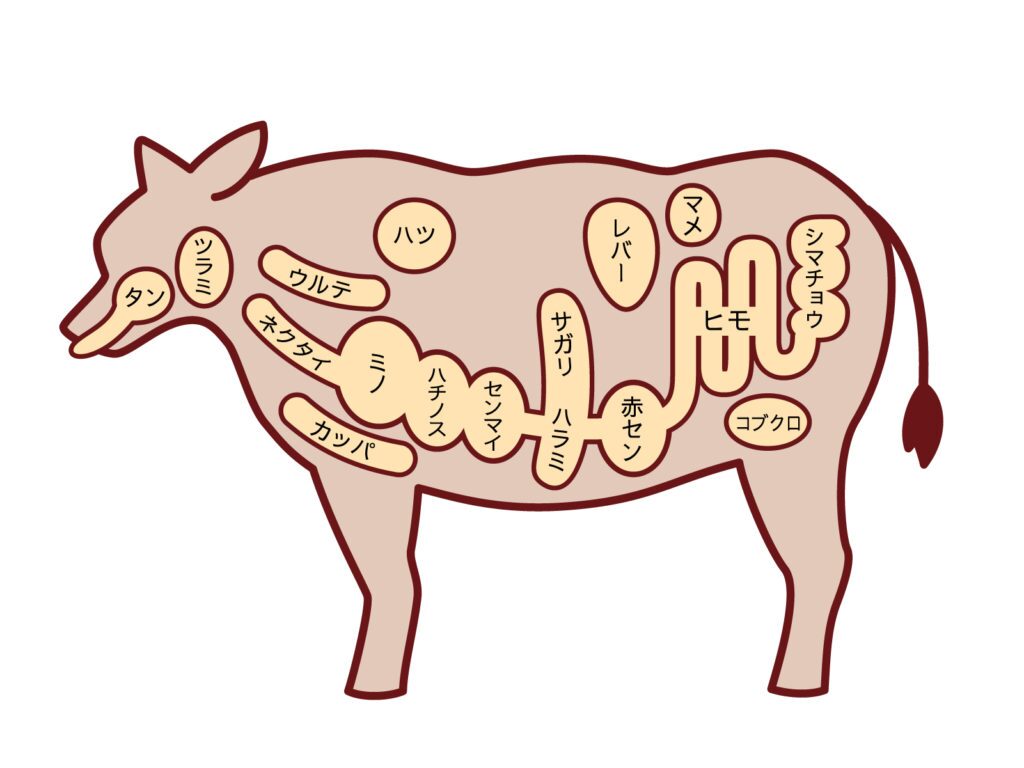
肝臓。鉄分、ビタミンなどの栄養価がとても豊富。
【 サガリ、ハラミ 】
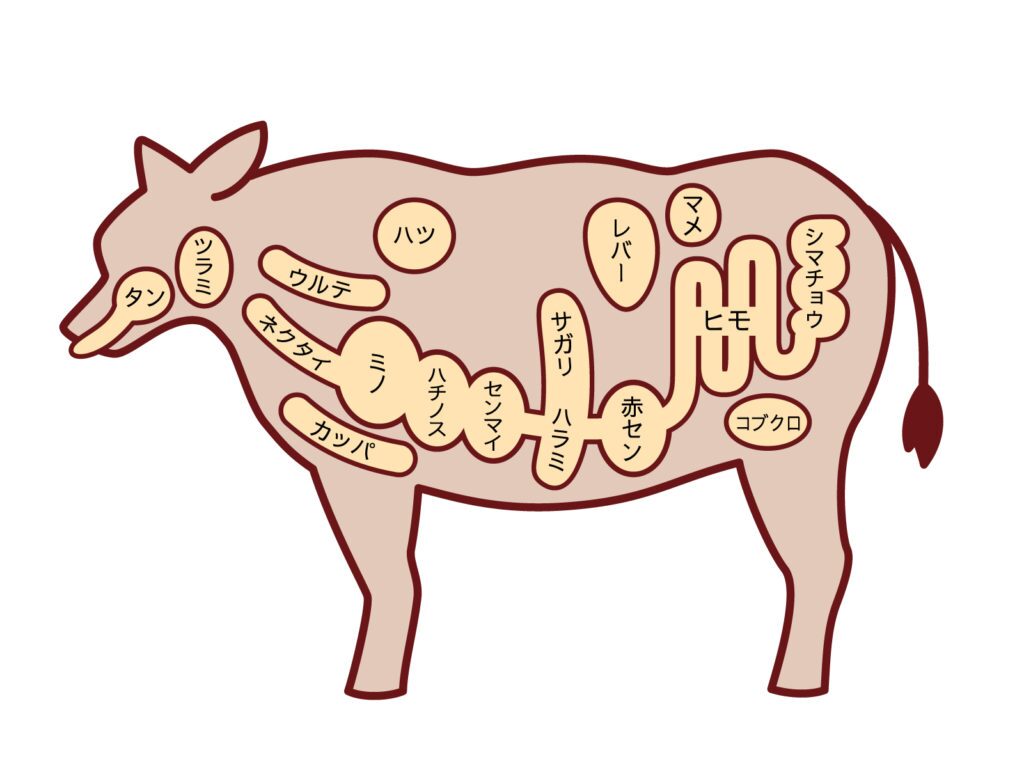
上の画像では同じ部位に見えますが、
サガリは横隔膜の肋骨側で、ハラミは横隔膜の背中側になります。
高たんぱく低脂肪。
【 ハツ 】
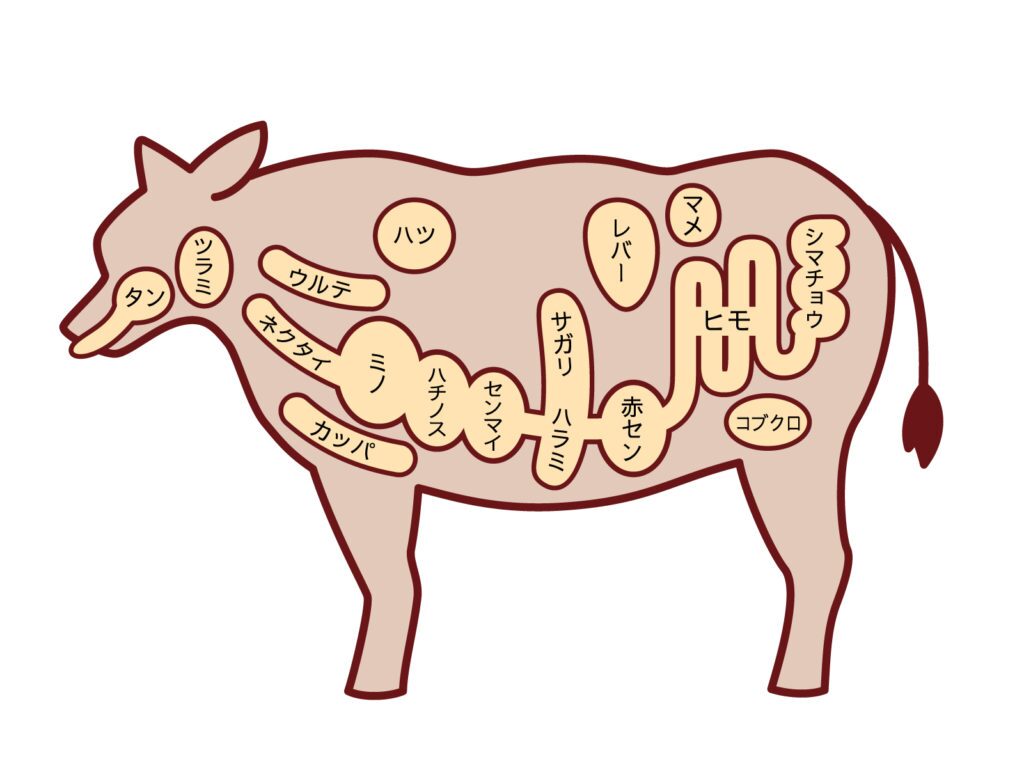
心臓。コリコリしていて栄養も豊富。
【 ミノ 】
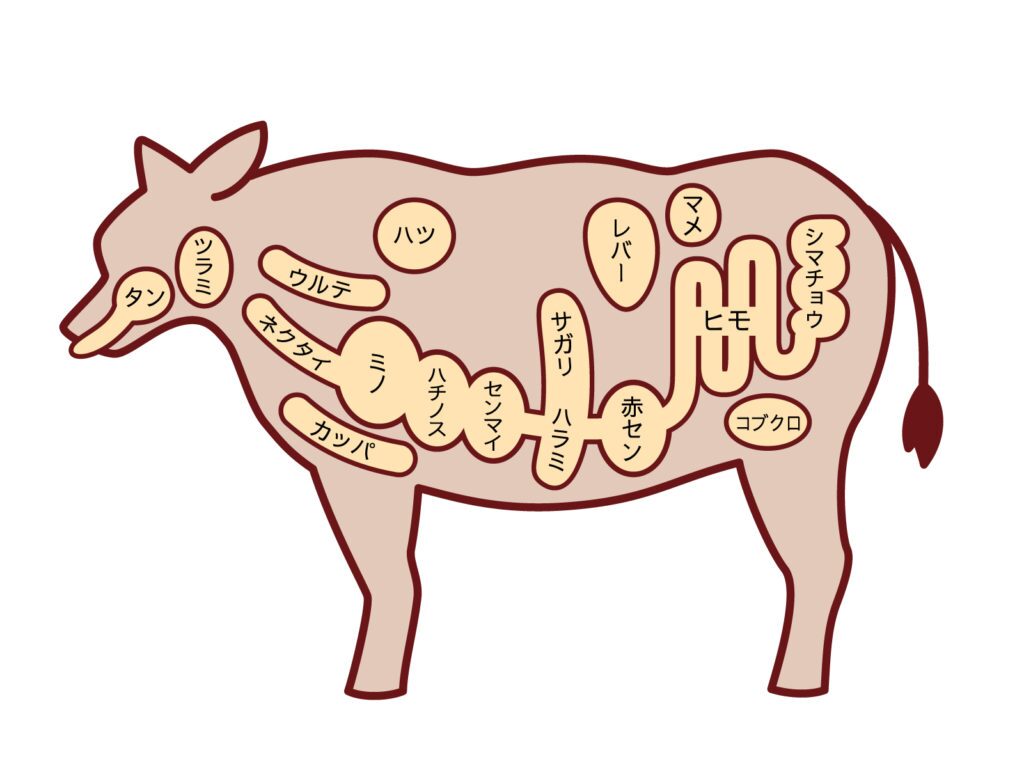
第一胃〔牛の胃袋は4つある〕。胃袋で一番大きく肉厚。
特に肉厚の部分を上ミノという。開くと、蓑(みの)に似ているため、
このように呼ばれているようです。
 (蓑)
(蓑)
【 ハチノス 】
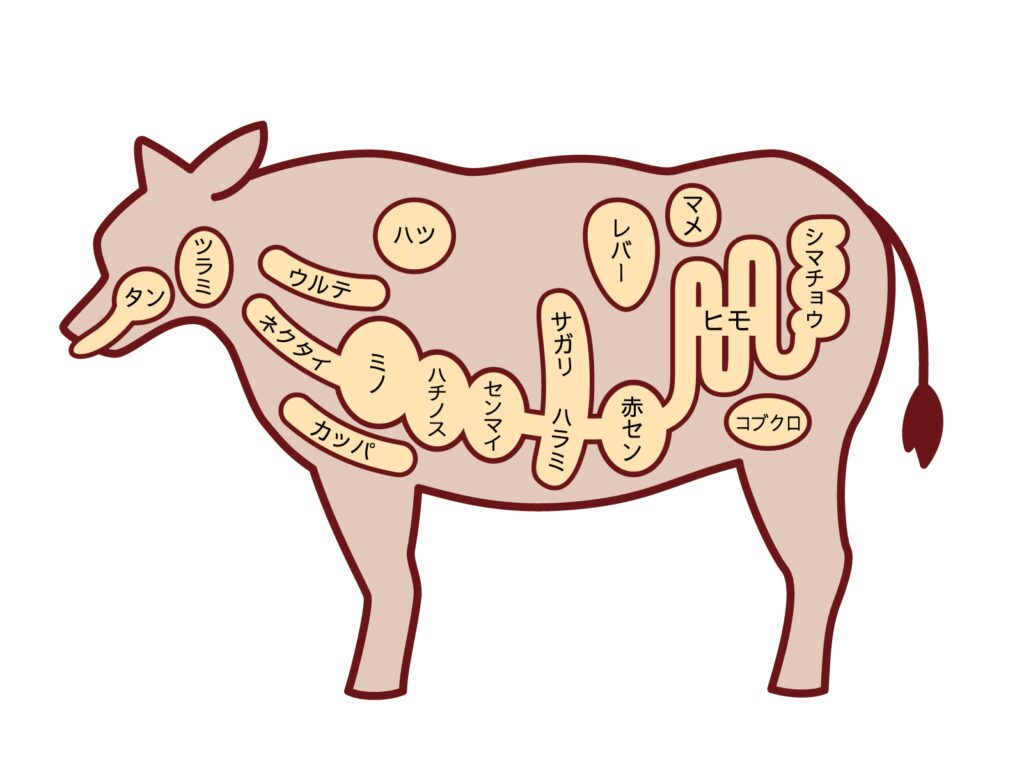
第二胃。ハチの巣のような形状をしている。※下処理をすると白くなります。

【 センマイ 】
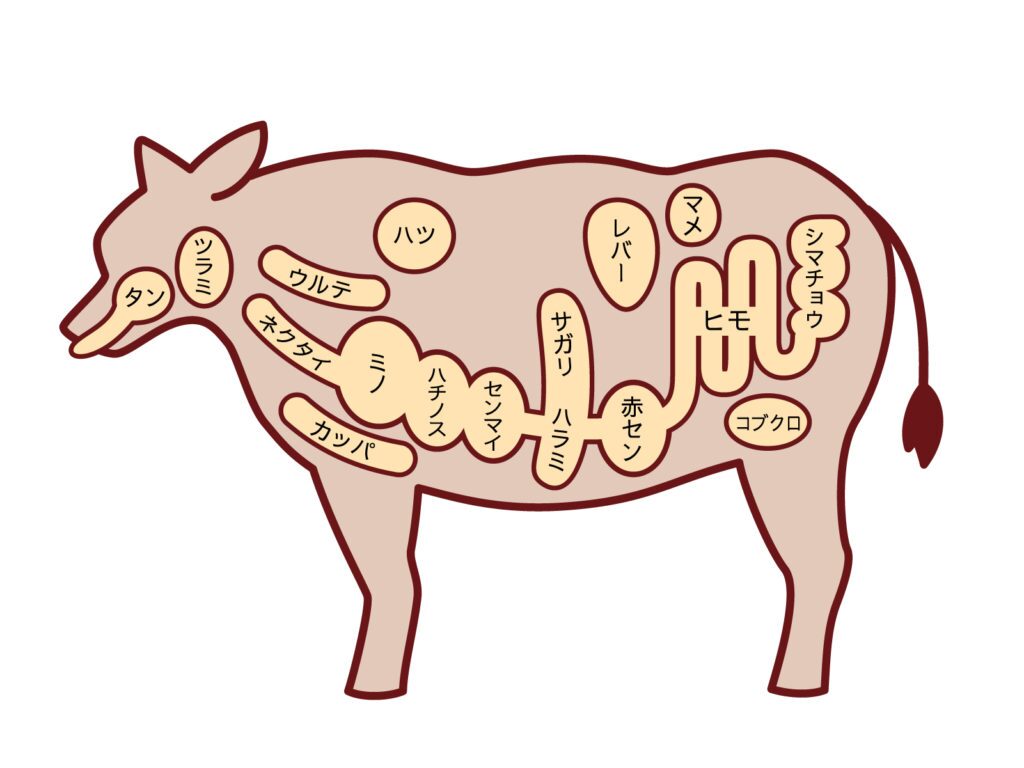
第三胃。ヒダが何層にもなっていて、千枚もあるように
見えることからセンマイと呼ばれています。

表面の黒い皮をはがしたものを白センマイといいます。
【 ギアラ 】
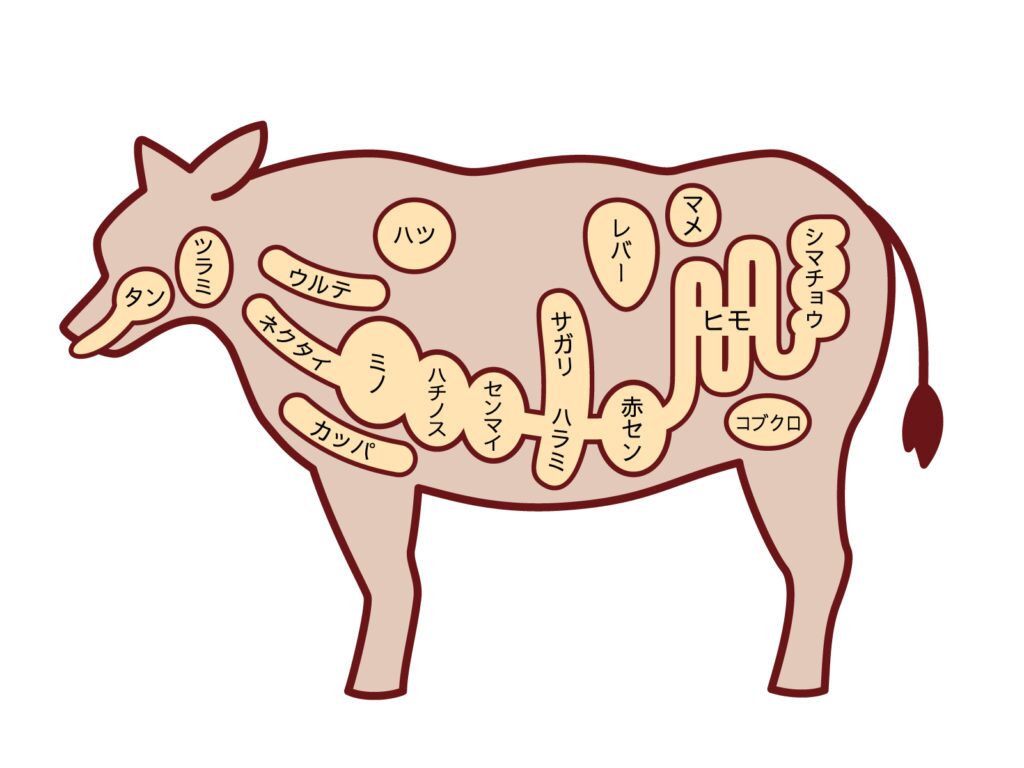
第四胃。脂肪を多く含む。
赤身がかった部分もあることから赤センマイとも言われます。

【 シマチョウ 】
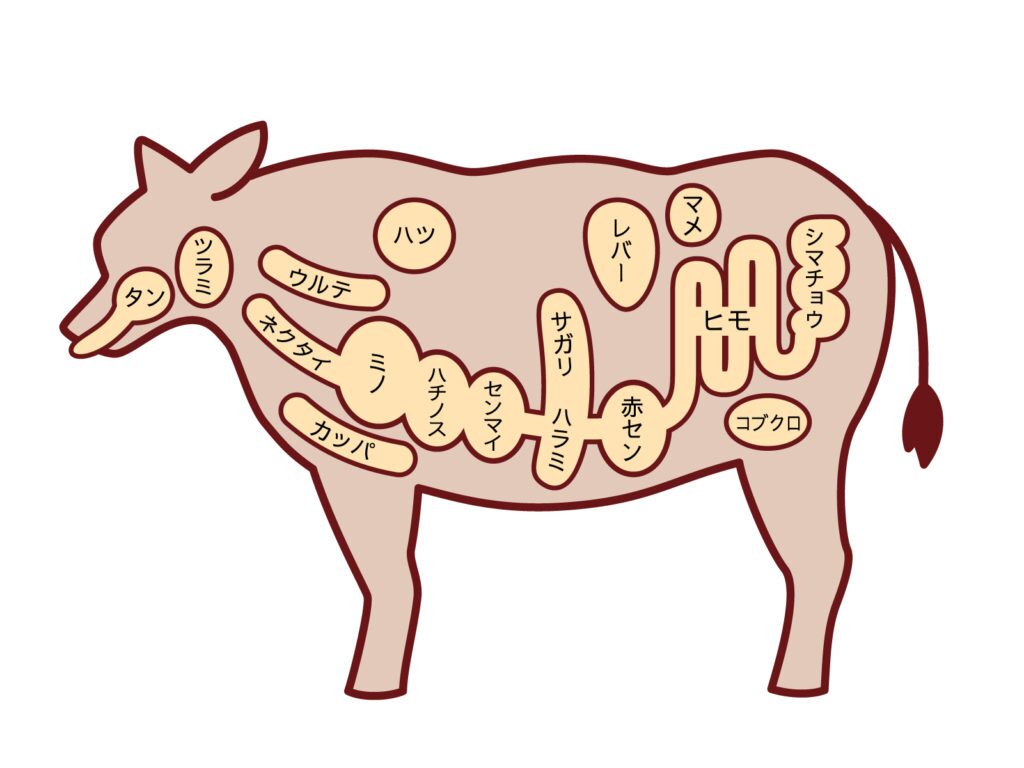
大腸。シマシマ模様ためシマチョウと呼ばれているようです。
脂肪がたくさん含まれている。
韓国語でテッチャン。
【 ヒモ 】
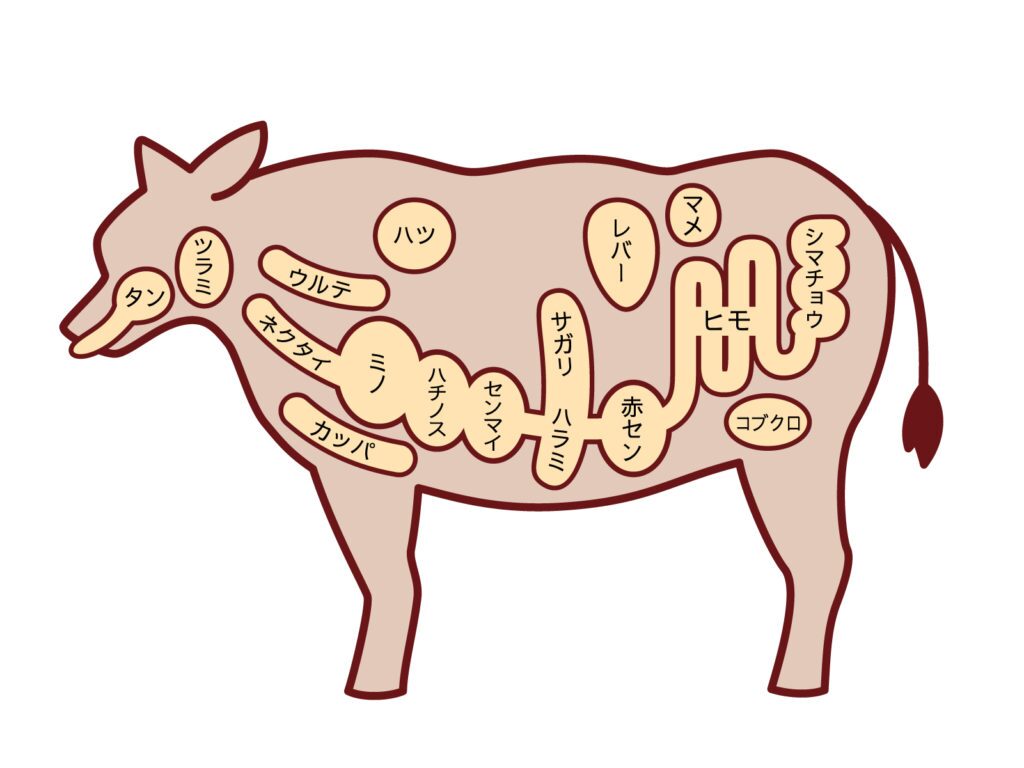
小腸。丸くコロコロしていることからマルチョウとも呼ばれています。
コラーゲンも多くプリプリしている。
大腸のテッチャンに小さいの『こ』をつけて、こてっちゃんになったそうです。