なぜ人の体温は36〜37℃?

私たち人間の体温は、体調が悪くなければ、いつ測ってもだいたい36〜37℃に収まっています。
でも、なぜこの温度帯なのでしょうか…
「もっと低くてもいいのでは?」「高めの方が元気そう」なんて疑問を持ったことはありませんか?
今回は、体温が36〜37℃である理由をわかりやすく解説していきます!
体温はなぜ一定に保たれるのか?

人間は「恒温動物(こうおんどうぶつ)」といって、外の気温に左右されず体温をほぼ一定に保ちます。
それは、体の中で起こる化学反応(かがくはんのう)〔物質が変化してエネルギーや新しい物質をつくるはたらき〕や、反応を助ける酵素(こうそ)〔反応をスムーズに進めるたんぱく質〕が、正しく働けるようにするためです。
- 体温が低すぎると → 反応が遅くなって体の動きが鈍くなる
- 体温が高すぎると → 酵素の形がこわれてうまく働かなくなる
つまり、36〜37℃くらいが人の体にとって一番効率よく動ける温度なのです。
36〜37℃は「酵素が働きやすい最適温度」
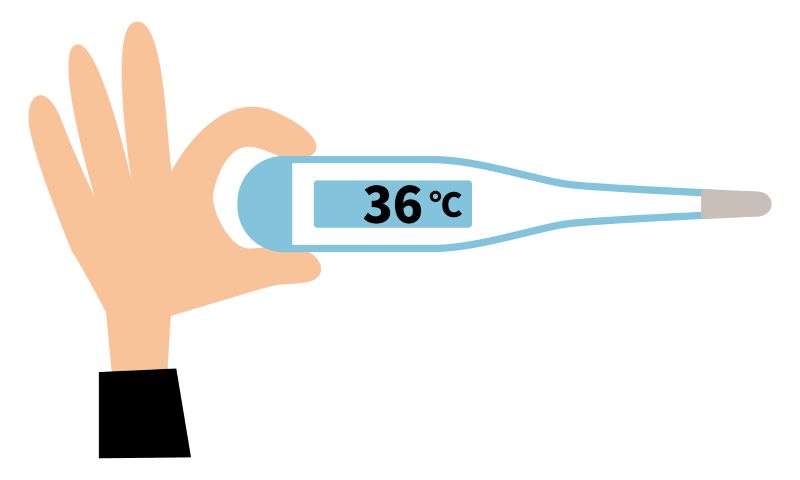
私たちの体では、食べ物を消化したり、エネルギーをつくったりと、ほとんどすべての活動に酵素が関わっています。
多くの酵素は約37℃前後で最も活発に働く性質を持っているため、その温度を中心に体温が維持されているのです。
35℃や38℃では体はどうなる?

- 35℃前後になると…
→ 体の反応が遅くなり、エネルギーをうまく作れません。手足が冷えて体が動きにくくなるのもこのためです。 - 38℃以上になると…
→ 酵素が熱に弱くなり形がくずれて働きが乱れ始めます。長く続くと体に大きな負担を与えてしまいます。
その結果、 - 細胞内の化学反応がうまく進まない
- エネルギーを作り出せない
- 免疫や臓器の働きが乱れる
といった影響が出てきます。
短時間なら体は回復できますが、長く高熱が続くと臓器に負担がかかり、意識障害や脱水など重い症状につながる危険性があるのです。
それでは、動物の体温はどれくらいなの…?

🐶 犬・猫
→ 38〜39℃
代謝が速く、体温もやや高め。小型犬や子犬は特に高くなりがちです。
🐇 ウサギ
→ 38.5〜40℃
小動物は体温が高く、外気温の変化にも敏感です。
🐁 ネズミ
→ 37〜39℃
とても高代謝で、寒さに弱いため体温維持に多くのエネルギーを使います。
🐴 馬
→ 37.5〜38.5℃
人間に近い範囲で安定しています。大型で代謝も安定しているため。
🐄 牛
→ 38.5〜39.5℃
反芻動物(はんすうどうぶつ)〔食べた草をいったん胃にため、再び口に戻してよく噛み直す動物〕は体温が比較的高めです。消化活動が活発なことも影響しています。
🐑 羊
→ 38.5〜40℃
牛と同じく反芻動物で体温が高め。毛が多いため暑さにも弱い。
🐔 ニワトリなどの鳥類
→ 41〜42℃
鳥類はほぼ例外なく高体温。筋肉を常にフル稼働しているため。〔飛ぶために多くのエネルギーが必要となる〕
🦆 アヒル
→ 40〜42℃
水鳥でも高温。羽毛で断熱しながら高体温を保っています。
🦉 フクロウ
→ 40〜41℃
夜行性ですが鳥類らしく高めを維持。飛翔にエネルギーが必要です。
🐍 ヘビ
→ 外気温依存(20〜35℃程度)
変温動物〔体温を自分で一定に保てず、外の気温に左右される動物〕の典型。日向ぼっこで体温を上げ動きを活発にします。
🐢 カメ
→ 外気温依存(15〜30℃程度)
寒いとじっとし、暖かいとよく動く。冬眠もこの仕組みです。
🐸 カエル
→ 外気温依存(10〜25℃程度)
両生類は外界に左右されやすく、寒いとすぐに活動が低下します。
🐟 魚類(例:金魚)
→ 外気温依存(水温とほぼ同じ)
水の温度が体温そのもの。急な水温変化に弱いのはこのため。
📌 まとめると
変温動物 → 外気温まかせ(爬虫類、両生類、魚など)
小型・高代謝の動物 → 体温が高い(ネズミ、ウサギ、鳥類など)
大型・安定した代謝の動物 → 人間に近い(馬、牛など)
人間の 36〜37℃ は「長時間活動できる安定した温度」であり、高すぎず低すぎず、代謝と寿命のバランスが取れた“最適温度” といえます。
まとめ

- 人の体温は36〜37℃で安定している
- 36〜37℃の理由は、酵素が最も働きやすい温度だから
- 低すぎると体の反応が鈍り、高すぎると酵素が壊れる
- この36〜37℃は「効率と安全のバランス」がとれている温度となる
つまり、私たちの体温が36〜37℃なのは偶然ではなく、「生命が最も生きやすい温度だから」だったのです!








