第1回 紅白歌合戦は正月の番組だった⁉

紅白歌合戦といえば、日本の大晦日を代表する国民的イベント。年の瀬に家族で見ながら1年を振り返る、そんな風景がすっかり定着していますよね。
でも実は、紅白歌合戦は最初から大晦日に放送されていたわけではないってご存じでしたか?
紅白の原点は、1945年12月31日にラジオで放送された「紅白音楽試合」という番組。
終戦直後の混乱の中、音楽を通じて人々に元気を届けようと企画されたもので、まだテレビもない時代、音声だけのラジオ番組でした。
この放送が好評だったことから、1951年1月3日に「第1回紅白歌合戦」として正式にスタート。ラジオ番組として復活したのが始まりです。
そして、1953年にはテレビ放送がスタート。この年はなんと、正月(1月1日)と大晦日(12月31日)の2回放送されました。
この大晦日放送を皮切りに、翌年からは毎年12月31日=紅白歌合戦の日として定着していったのです。
紅白歌合戦の歴史的背景

紅白歌合戦が誕生した背景には、戦後の日本の復興と国民の団結を促す意図があったといわれます。
1950年代の日本は、戦争からの復興が進んでいる時期で、多くの人々が希望を持って新しい年を迎えようとしていました。
そんな時期に、音楽を通じて国民が一つになることを目的として、NHK(日本放送協会)は紅白歌合戦を企画したそうです。
視聴者参加型の対抗戦が多くの人々に受け入れられる

紅白歌合戦は、視聴者参加型の対抗戦というスタイルも大きな魅力となりました。
紅組(女性歌手)と白組(男性歌手)に分かれて、さまざまなアーティストがそれぞれの歌を披露し、視聴者や会場の観客がどちらが良かったかを投票します。
これも、戦後の日本で多くの人々が音楽を通じて一つになるための仕掛けでもあったようです。
戦後の混乱から立ち直り、日本の経済が再び活力を取り戻していく時期に、「紅白の歌手対決」という形式は団結を象徴するものとして、多くの人々に受け入れられたのです。
1980年代以降の紅白歌合戦

時代が進むにつれて、紅白歌合戦も様々な進化を遂げました。1980年代以降になると、海外のアーティストがゲストとして参加することも増え、歌唱だけでなくダンスやパフォーマンスも見どころの一つになっていきました。
また、平成に入ると、ビジュアル系バンドやJ-POP、アニメソングなど、ジャンルも多様化。様々な年齢層で楽しめる国民的イベントとして、さらにエンターテイメント性を高めていったのです。
現在では、紅白歌合戦はその年に流行した音楽や話題のアーティストが集う場であり、どの曲が歌われるのか、どのパフォーマンスがあるのかが注目されています。
SNSでも多くの視聴者がリアルタイムで感想を共有し、さらに一体感が増しているのも現代ならではの特徴です。
また、紅白歌合戦が年末に放送されるということで、「これが終われば新年」といった年末の風物詩として高揚感が感じられるのもこの番組の魅力なんでしょうね!
最後に
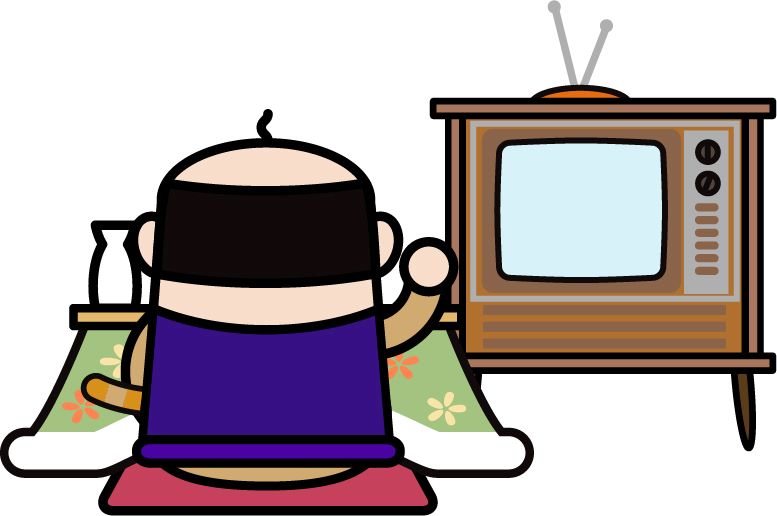
紅白歌合戦が正月のイベントから大晦日の恒例特番へと変わった背景には、日本人の「年越し文化」が色濃く反映されています。
一年の締めくくりとして紅白を観賞し、その後に除夜の鐘を聞きながら新年を迎えるという、日本ならではの習慣が多くの家庭に定着してきたのです。

紅白歌合戦は、単なる音楽番組にとどまらず、日本の文化や家族の絆を象徴する存在とも言えるのかもしれません。




