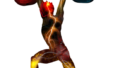白身魚、赤身魚の違い

刺身や寿司ネタを見てもわかるように、魚の身は赤かったり、白かったり、サーモンピンク色だったりと色鮮やかですが、そもそもどうして色が違うのでしょうか…?
赤身と白身の定義
魚の赤身と白身の区分には定義があり、ヘモグロビン〔血液中の赤色の色素、鉄を含む色素たんぱく質〕と、ミオグロビン〔筋肉中にある、ヘモグロビンに似た色素たんぱく質〕の含有量によって分かれ、100g中に10mg以上含まれると赤身となるようです。
※色素たんぱく質は、常に泳ぎ回って暮らす魚〔回遊魚〕が、呼吸での酸素を取り込みやすくするのに必要となります。
それでは、『サーモン』は白身? それとも赤身?
ここで、どちらに分類されるか疑問な魚が出てくるのですが…
まずは、『鮭(サーモン)』
赤身、白身どっちなのでしょうか?

色だけを見れば赤身のようにも感じてしまいますが、鮭が餌としているオキアミ↓やエビなどの甲殻類の赤の色素〔アスタキサンチン〕によってサーモンピンク色になっているようで、元々は白身なんだそうです。

そのため、養殖の場合はピンク色ではなく白色の鮭になる事もあるようです。
『青魚』は白身?それとも赤身?


(サバ)
次に、サバ、サンマ、イワシなどの『青魚』
青魚と呼ばれている訳ですが、どちらになるのでしょうか…?


(サンマ)
青魚とは?
まず、青魚と呼ばれる一般的な定義は、先ほどのヘモグロビン、ミオグロビンでの赤身に分類されていること、そして背が青く見える魚であること、それでいて近海でとれる小型の回遊魚〔生涯を移動しながら生活する魚〕を指すことが多いということです。
※背が青く見える理由は、脂肪酸という油であるDHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)を多く含むためです。
そのため、青魚は赤身であることが分かります。


(イワシ)
※白身のように見えても、赤身と呼ばれる魚には白身に比べ血合い〔魚特有の背身と腹身の間にある赤色の筋肉繊維〕が多くあります。
ブリ、サワラ、カツオなどは青魚にも分類することができる
ちなみに、ブリ、サワラ、カツオなど中型以上の魚は一般的には青魚とはあまり呼ばれていませんが、色素たんぱく質で見れば、青魚にも分類することができるそうです。
そのため、赤身となります。


(ブリ)※ブリはアジ科


(サワラ)※サワラはサバ科


(カツオ) ※カツオはサバ科