クリスマス・イブは前日ではない?

12月24日のクリスマス・イブと聞くと、クリスマスの前日『eve(イブ)』と思ってしまうのですが、実は、クリスマスの夜『evening(イブニング)』というのが本当は正しいようです。
それでは、どうしてイブ=前日という認識になってしまったのでしょうか…?
キリスト教の「教会暦」の秘密
実は、キリスト教には、昔から使われていたキリスト教会特有の暦(こよみ)、『教会暦(きょうかいれき)』〔元々のユダヤ暦。イエス・キリストの生涯の出来事を1年周期に当てはめた暦〕というものがあるのですが…

その教会暦での一日は、「日没から始まり~日没に終わる」という考え方になるそうです。

そのため教会暦でのクリスマス12月25日は、現在使われている暦に当てはめると12月24日の日没(日の入)~次の日25日の日没(日の入)までということになります。
つまり、前日というよりは、当日の夜だったんですね。
教会暦25日クリスマス夜 = 現在の暦24日クリスマス夜(evening)

教会暦では、クリスマスが夜から始まるため、現在の暦での、前夜が一番盛り上がっていたというわけなのです。
クラッシック音楽の定義とは…?クラッシック音楽の歴史について
クリスマス・イブの語源

「Christmas Eve」という言葉には、“evening(夜)”という意味が隠れています。
もともと英語の古い言葉で「even(イーヴン)」という語が「evening(夜)」を表していました。この「even」の最後の音(-n)が脱落して「eve(イーヴ)」という形になり、
“Christmas Eve”=“クリスマスの夜” という意味になったのです。

つまり、「Eve」は“前日”という意味ではなく、“夜(evening)”の古い言い方がもとになっているのです。
本来クリスマスは何をする日…?

日本ではあまりピンとこない人の方が多いかと思いますが、クリスマスというのは、イエス・キリストがこの世に生まれてきたことを祝う祭典である『降誕祭(こうたんさい)』のことを言います。

誕生ではなく、降誕という言い方をするにはいくつか説があるようなのですが、一つは、新約聖書(しんやくせいしょ)〔1~2世紀頃キリスト教徒により書かれた文書〕にはイエスの誕生日のことが記載されていなく、はっきりと分からないのが大きい理由のようです。
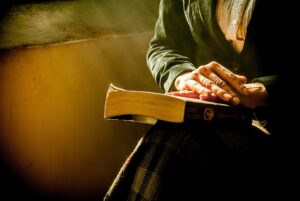
イエスの死後、数百年もたった4世紀頃に12月25日を降誕祭という日にしたと考えられているのですが、それは、当時のローマ帝国時代、ローマ歴での冬至(とうじ)〔1年で最も夜が長く、昼が短い日〕を祝う日が12月25日(太陽神の誕生日)だったからとされています。
※当時の冬至の考えた方ですが、1年で最も夜が長く昼が短い日であるため、太陽が誕生した日と信じられていたそうです。

そのため、冬至を境にだんだんと光が多く差す(太陽が誕生した日と考える)=イエス・キリストと重ねられ、この日を降誕祭にしたのではないかと言われているのです。
※ローマ帝国とは… 紀元前8世紀頃に誕生し1,200年以上も続いた西洋古代最大の帝国。ラテン人〔イタリア中西部のラティウムに住んでいた民族〕によって築かれる。

このように、イエス・キリストが実際に誕生した日が12月25日とは限らないのですね。
ちなみに、キリスト教圏では、クリスマスは12月25日だけでなく、翌年の1月6日(公現祭)〔イエス・キリストが神の子として世に現れたことを祝う日〕までの12日間にわたって祝われます。
日本のお正月のように、年末年始をまたぐ大切な期間とされています。




